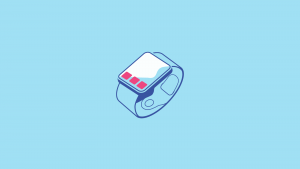この記事の要点
- 見守り介護とは要介護者のトラブル時にすぐ援助できる態勢を整えておくこと
- 見守り介護の目的は事故防止・急変対応・要介護者の自立支援
- IT技術で見守り介護が楽になる
- さらに見守り介護を効率化するための研究が世界中で進められている
介護施設での重要な業務のひとつが「見守り」です。
介護施設における見守りは、ただ利用者を「見る」だけでなく、目的をもって行われています。
今回は介護施設で利用者の見守りをする目的と、介護職員の見守り業務を支援するIT技術、そして、より一層効率的に見守り業務を行うために世界中で行われている最新研究を紹介します。
目次
介護施設における「見守り」とは

まずは介護施設で職員が行う見守り業務とはなにかについて、改めて確認しましょう。
介護施設における「見守り」とは、介護職員が利用者の状態を把握できる状態にあり、利用者が何らかの助けを必要としたときにいつでも介助や援助が行える態勢を整えておくことです。
見守り業務では直接利用者の身体に触れることはありません。また介護職員の業務ルーティンに「見守り」が含まれるわけでもありません。
見守りは介護職員が日々の業務を行いながら、常に目線を利用者に向けるなどして行われています。
見守りの目的

介護施設における見守り業務には以下3つの目的があります。
急変に備える
介護施設に入居している高齢者の中には、持病のある方もいます。また入居時には健康状態に問題がなかった利用者でも、いつ健康状態が悪化するかわかりません。
介護職員は利用者の健康状態を常に確認し、体調不良や持病の急変にすぐに気づくためにも見守ることが必要です。
事故を防止する
筋力が衰えた高齢者にとって、生活上の事故は身近にある危険と言えます。
足元がふらついて転ぶ、ベッドから起き上がろうとしたときに手すりがうまくつかめずに転落するなど、突然の体調不良と同じく事故はいつ起こるかわかりません。
また車椅子や介護ベッドなどの福祉用具を使用している状態でも、その福祉用具に起因する事故が起こり得ることが厚生労働省資料などにまとめられています。
あらかじめ事故のリスクを減らすと同時に、もし事故が起こったときにもすぐに気づけるように見守ることは重要な業務です。
自力での活動を促す
事故のリスクを減らすために介護職員が1から10まで利用者の面倒を見てしまっていては、利用者の自力を引き出すことができません。
「介護のしすぎ」により利用者の日常生活自立度が低下することが予想されます。
利用者の安全を守るために見守りつつも、利用者が自分でできる範囲の生活行動にはあえて手を出さず自分自身で行ってもらうことで、利用者の自力での活動を促す機会が作れるのです。
「見る」と「見守り」の違い

上記で説明したような見守り業務の目的を達成するためには、介護職員はただ「見る」だけでは不十分です。
以下では見守り業務の「見る」と「見守り」の違いを説明します。
利用者の動きの事前予測
利用者の動きを予測し、危険動作につながる行動をあらかじめ察知できれば、事故のリスクは大きく軽減できます。
起床してすぐトイレに行く習慣の利用者であれば、利用者が起床した時点ですぐに居室に向かえば転倒事故も避けやすくなるでしょう。
また問題行動を起こしやすい利用者についてはデイルーム内での他の利用者との距離をおくなど、複数の利用者に配慮しながらの見守りが大切です。
介護職員間の情報共有
介護職員の1人が察知した危険予測も、他の介護職員とその情報が共有できなければ意味がありません。
危険予測した介護職員がシフトに入っていないときに事故や急変が起きる可能性があるからです。
巡回などの見守り業務を行う上では、介護職員は「ただ見るだけ」では終わらせず、引継ぎや介護記録への記載などにより他の介護職員に気づいた情報を適切に伝える必要があります。
介護施設における見守りを支援するIT機器

この記事の最初に説明したとおり、見守り業務はそれ単体で介護職員が行う業務ではありません。
配膳の準備やリネン交換をしながら、またときには他の利用者の身体介助を行いながら別の利用者の見守りを行う必要があるなど、マルチタスクが必要になる見守り業務は介護職員の精神的な疲労につながります。
介護職員の見守り業務の負担を軽減するため、最近ではIT技術を活用したいろいろな見守り支援機器・システムが開発されています。以下の記事で紹介している見守りロボットもそのひとつです。
▶介護用見守りロボットとは? 導入メリット・利用者の声も紹介
具体的にはどのような見守り支援機器やシステムがあるか見ていきましょう。
人感センサー
人感センサーとは介護施設内の壁や天井、家具などにセンサーを設置し、利用者の動きを検知するセンサーです。
利用者の居室だけでなく、介護施設の玄関やエレベーター前などにも設置され、利用者の徘徊防止としても利用されています。
検知方法には温度変化や赤外線の通過、また超音波を利用した人感センサーがあります。
ベッドセンサー
ベッドセンサーとは利用者の居室ベッドにセンサーを設置し、利用者の離床を検知するセンサーです。
ベッドマットレス上に敷くタイプやベッドの脚下、離床時に利用者が体を支えるレールに取り付けるタイプなどがあります。
バイタルセンサー
バイタルセンサーとは利用者の心拍や呼吸などの生体情報や、運動・睡眠などの利用者の行動情報をチェックするセンサーです。
ベッドセンサーのようにベッドマットレス上に敷く形状のバイタルセンサーだけでなく、利用者の手首に装着するスマートバンド状のバイタルセンサーもあります。
効率的に見守り介護するための研究を紹介

高齢者介護は、いまや世界中のどの国でも大きな社会問題となっています。
そのため、効率的に介護をするためにはどうしたら良いかの研究が、世界各国で進められています。
AIなどの最新技術を用いて科学的に介護の見守りを行おうという研究もそのひとつです。
以下からは当サイトがこれまでに紹介した、見守り介護に関する最新研究を4つ紹介します。
離床センサーへのAI活用
秋田県立大学と山口大学の共同研究グループは、見守り機器の離床センサーから得られた情報をAIに覚え込ませ、要介護者が離床するタイミングを予測するシステムを開発しました。
2種類のセンサーを併用し、複数のAIアルゴリズムを使用することでこれまでの研究よりも高い精度で離床タイミングが予測できるという研究成果が得られています。
しかしまだ改善すべき点も多く、実用化に向けてはさらなる工夫と実証実験が必要とのことです。
秋田県立大学と山口大学の共同研究について詳しくは以下の記事をご覧ください。
▶AIと離床センサーを組み合わせて離床行動を高度認識 秋田県立大など開発
介護職員の見守り情報共有
見守り業務による介護職員の負担を軽減するための研究も進められています。
ノルウェーUniversity of Ouluが行った研究は、各種見守りセンサーで得られた情報をアプリで一括管理し、すべての介護職員にデータを共有できるというものです。介護職員間のデータ共有はICT(情報通信技術)によって行われます。
さまざまな介護業務を並行して行わなければいけない介護職員ですが、ICTによって見守り業務を効率化できる可能性が示唆されています。
University of Ouluの研究成果は以下の記事でご確認ください。
▶介護士の仕事効率を改善し、離職を防ぐ センサー型見守りツールをAppで管理する最新テクノロジー
認知症高齢者の逸脱行動を検出
認知症高齢者の逸脱行動(徘徊、転倒、不眠など)を検出するシステムについては従来からも各地で研究が進められていますが、韓国のSejong Universityが行った研究では、見守りセンサーを活用して認知症高齢者の逸脱行動を検出しようと考えました。
センサーから得られたデータをAIが分析し、認知症高齢者の行動や心理症状を判定する研究です。
研究の結果、いくつかの特定の逸脱行動については高い精度で判定はできたものの、認知症高齢者の逸脱行動には多くの種類があるため、実用化に向けてはさらに長期的なAI分析が必要とされるところです。
Sejong Universityの研究については以下の記事で紹介しています。
▶AIとセンサーで認知症高齢者の行動・心理症状を検出。韓国の研究グループが開発
見守りセンサーから高齢者の社交性まで検出
アメリカのカリフォルニア州立大学とテキサスA&M大学による共同研究グループが行った研究は、「スマートカーペット」を利用した興味深い研究です。
センサーが内蔵されたカーペット(スマートカーペット)を用いて要介護者の歩行状態を検知し、転倒などの事故リスクを予測しながら、さらに要介護者の社交性まで測ろうとしています。
このスマートカーペットが実用化されたあかつきには、独り暮らし高齢者の遠隔見守りにも活用できるだろうと考えられています。
カリフォルニア州立大学とテキサスA&M大学の研究について詳しくは以下の記事をご覧ください。
▶センサーで人の動きを検知する「スマートカーペット」 高齢者の転倒や社交性など検出・分析
まとめ
今回は介護職員の見守り業務について解説しながら、見守り業務を効率化できるIT機器・システムと最新の研究成果を紹介しました。
高齢者が安全に暮らしを送るためには、介護者など周囲のあたたかい見守りの目は欠かせません。
人間の目とテクノロジーをどちらも活用し、効率的かつ効果的に日々の見守りを行っていきましょう。


 はてブ
はてブ