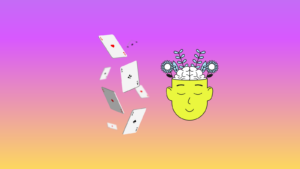この記事では、介護士の教育・訓練をロボットで効率化する日本の研究を紹介します。
目次
介護士の教育・訓練を取り巻く環境
高齢化や、それに伴う社会保障制度の改革が進む中、介護の役割は大きくなっています。高齢者の自立や幸福な生活を実現するために、国としては介護施設や介護サービスを十分に備え、多くの介護士を育成する必要があります。
ちなみに国内で個人が介護士になる方法は、以下の3つのルートがあります。
- 無資格・未経験で介護現場に飛び込む(働きながら資格取得を目指す)
- 介護職員初任者研修を修了してから介護現場で働く
- 福祉系の学校に進学してから介護現場で働く
参考▶︎介護士になるには!これから介護の道に進む人のための完全ガイド(介護ワーカー)

ただ、熟練の技術を持った介護士になるためには資格を取得するだけでは十分ではありません。現場で実務経験を積み、教育を受けたり訓練をしながら技術を向上させる必要があります。
既存の教育サービス
介護士の専門性を担保し、求められる役割を担うために必要な知識等を習得するために、世の中には研修のサービスがあります。
日本介護福祉士会は、「介護福祉⼠基本研修」「ファーストステップ研修」「認定介護福祉⼠養成研修」を3つの軸として多くの研修を提供しています。さらに、研修講師を要請する研修も実施しています。

ヒューマンライフケア株式会社は外国人介護士や介護事業者、企業・団体を対象に多くの研修や講習を提供しています。資格取得の対策だけでなく、リーダーシップやサービスマナー、コンプライアンスに至るまで包括的に対応しています。
今後の課題
上記のように介護士を教育する外部サービスは存在しますが、やはり現場で訓練を積むことも重要です。
先輩の介護職員に教わりながら実務をこなしていく間に技術が向上していくこともあります。介護事業所によっては教育係を明確に任命する場合もあり、任せられた職員は新人・未経験介護士を教育するにあたって工夫する必要が出てきます。
参考▶︎教育係は必見!新人介護職員の指導で気をつけたい5つのポイント(介護ワーカー)
介護士の教育や訓練の過程においては、どうしても高齢者本人の協力が必要になる場合があります。しかし同時に、高齢者の負担は極力避けるべきでもあります。

そのため今後の課題として、介護士の技術を向上させるための教育・訓練過程における高齢者の負担を減らすための新たな取り組みを導入していくことが出てきます。
生身の高齢者に代わるリアルな高齢者ロボット
立命館大学の研究グループは高齢者の負担を軽減するために、リアルなロボットを用いて介護士が高齢者の痛み(疼痛)を読み取ることで介護スキルを向上させる方法を研究しています。その内容を以下で紹介します。

参照する科学論文の情報
著者:Miran Lee, Dinh Tuan Tran and Joo-Ho Lee
機関(国):立命館大学(日本)
タイトル:3D Facial Pain Expression for a Care Training Assistant Robot in an Elderly Care Education Environment
URL:doi.org/10.3389/frobt.2021.632015
ロボットが「顔」で痛みを表現する
介護方法を学ぶためにロボットを活用する研究は2007年頃から行われてきました。しかし、高齢者の「感情」に関わる介護の学習に関してはロボットを活用する研究は行われてきませんでした。その理由は、介護の動きに合わせてロボットが顔で(視覚的に)感情を表現するテクノロジーが未発達だったためです。一方で介護現場では、高齢者が痛みを感じないような力加減や動きで介護を行うことは重要です。
そこで立命館大学の研究グループは、体の痛みに合わせてロボットが痛みを顔で表現するシステムを新たに開発しました。具体的には、現実の高齢者が痛みを感じた時の表情を3Dスキャンしてアバター(仮想上の姿)を作成し、ロボットの表情に適用したのです。開発された、痛みを顔で表現するロボットはCaTARoと名付けられました。

CaTARoは顔だけでなく関節もリアルに作られました。
高齢者はしばしば関節がこわばり、介護士は関節をほぐすための運動をサポートする介護を行うことがあります。その際、介護士は高齢者の痛みを観察しながら力や動きを調節する必要があります。
介護士がCaTARoの関節を動かす際に、力加減を誤る(過剰な動きをする)とCaTARoの顔から痛みの感情が表現される仕組みが搭載されました。

介護士がロボットから痛みを読み取る実験をした結果・・・

介護訓練にCaTARoを用いる実験には9名が参加しました。内訳は、介護専門家5名と一般の学生(介護が専門ではない)4名でした。
実験手順は以下の通りです。
- 専門家が肘関節を運動させる介護動作をCaTARoで行いました。
- 学生がその映像から介護動作方法を学びました。
- 学生が(訓練なしで)見よう見まねで介護動作の演習を行い、力加減などを計測しました。
- 学生がCaTARoを用いて介護動作を30分間訓練しました。
- 練習後、学生が2回目の介護動作の演習を行い、再び力加減などを計測しました。
以上の実験手順により、CaTARoを使用した介護訓練の有効性が分析されました。
結果、学生の介護スキルは30分間のCaTARoを用いた訓練で向上していることがデータで確認されました。
また実験後には5人の介護専門家に対して専門的なアンケートが行われました。
アンケートの結果、「将来的に、肘関節の運動に関してCaTARoを用いた介護訓練を行うことは良いことか?」という質問項目に対して5点満点中平均4.4点のスコアが出ました。
さらに2人の学生に対して行われたアンケートでは、「学生や初心者のトレーニングツールとしてCaTARoシステムにどの程度満足していますか?」という質問項目に対して5点満点中4.3点のスコアが出ました。
本当にロボットは生身の高齢者の代わりになるのか
上記の実験は参加者の数が必ずしも多くはなかったため、さらに規模の大きい実験を行なってシステムの有効性を確かめる必要がありそうです。しかし少なくとも「痛みを顔で表現するロボットを用いた訓練により、介護技術が向上する」という可能性は確かに見出されました。
今後、あらゆる介護訓練においてロボットが生身の高齢者の代わりになるのかどうかは分かりませんが、ある程度の期待はできるかもしれませんね。
ちなみにCaTARoの動きや仕組みに関しては、立命館大学の研究グループ公式YouTubeで映像が公開されています。関心のある方はご覧になってください。
まとめ
この記事では、介護士の教育・訓練をロボットで効率化する日本の研究を紹介しました。
介護士のように人と直接触れ合って支える仕事を行う職業に就くには、資格などのハードルはもちろんですが何より「人の健康や命に影響を与える」というプレッシャーを乗り越える必要があります。
ロボットを用いて効率的に訓練できるようになると、プレッシャーを乗り越えやすくなるかもしれませんね。
このようにスキルを向上させるためのDXは、人の温かみを現場に残しつつ、さらに質の高いサービスをもたらすものですね。
介護とロボットに関する他の話題が気になる方は以下の記事もおすすめです。
参考▶︎「自動シャワー装置」ユーザー体験の調査結果 〜高齢者・介護スタッフ両方の視点から〜
参考▶︎アシストスーツは高齢者のADL低下予防にも役に立つ
参考▶︎【宇井吉美】排泄センサーHelppadの株式会社aba代表インタビュー(前編)たゆまぬ研究開発、現場との約束。


 はてブ
はてブ