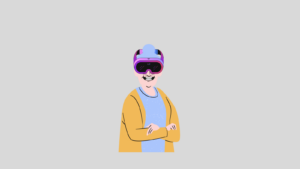「ロボット」という言葉に、人生で初めて出会ったのはいつですか?
戦隊モノのテレビ番組?それとも、スーパーのおもちゃ売り場?
その響きに、大人になっても、否応なしにわくわくしてしまう人も多いのではないでしょうか。
問題を解決する凄い存在、というイメージですが、この先の高齢化社会の問題については果たしてどうでしょうか。
今日のテーマは「介護ロボットの将来」です。
いつものように、要点をまとめてみます。
この記事の要点
- 認知症の人々はソーシャルロボットによって助けられるかもしれない
- 新しい介護ロボット「MARIO」が国際的に研究されている
- 業界のほとんどの意見は、好意的だった
※なお、マリオと聞くと任天堂のキャラクターが思い浮かびますが、今回のMARIOは無関係のものです。
目次
まるでドラえもんやベイマックスのような存在
今日はハードウェアの話
高齢者が、身体的にだけでなく、社会的に健康を得られるためには、周囲とのコミュニケーション(社会参加)が重要だと言われています。国内でも以前から、高齢者の孤独について、調査や防止策の検討が行われてきました(厚生労働省「孤立死防止対策」より)。
実際、高いレベルで社会参加している高齢者は、認知症やうつ病にかかりにくいことが知られています。彼らの孤立を救うために、テクノロジーの発展した現代だからこそ出来ることはないでしょうか。
そんな訳で、本日も引き続き高齢者の認知症をテーマに、新しいテクノロジーの可能性を深堀りしてみたいと思います。
テクノロジーと一言でいっても、AIの話やVRの話(*)は、どちらかと言えばソフトウェア(目に見えないもの)の話でした。
今回は、ハードウェア(目に見えるもの、物理的なもの)のお話です。
(*それぞれ、タグを経由して関連記事を一覧できます。)
アイルランドの研究者たちは、人間のかわりに被介護者と対話する「ソーシャルロボット」が、介護関係者にどれくらい受け入れられているかを調べたようです。その報告書が興味深いので、本記事で紹介したいと思います。
★この記事で参照している科学論文の情報
著者:Dympna Casey, Eva Barrett, Tanja Kovacic, Daniele Sancarlo, Francesco Ricciardi, Kathy Murphy, Adamantios Koumpis, Adam Santorelli, Niamh Gallagher, Sally Whelan
タイトル:The Perceptions of People with Dementia and Key Stakeholders Regarding the Use and Impact of the Social Robot MARIO
URL:doi.org/10.3390/ijerph17228621
ソーシャルロボットの最先端
ソーシャルロボット(あるいはコンパニオンロボット)とは、その名の通り、人間と対話する能力をもつロボットのことです。
認知症の方々をサポートするソーシャルロボットの可能性については案外まだまだ研究されておらず、これから開拓されていく分野と言えます。
これまでの研究ですでに、分かっていることがあります。それは、現場ではたらくソーシャルロボットは、被介護者のネガティブな感情を軽減して、介護体験の質を向上させるということです。
ちなみに、介護の現場でロボットを使用する際は、介護者中心で動くように組み込むのが介護者に対しても良い結果をもたらすようです。
介護現場向けのソーシャルロボットとして国際的に研究されている最先端のプロジェクトの一つに、「MARIO」プロジェクトがあります。
MARIOは、6カ国からあらゆる分野のスペシャリストが結託して開発を進められているロボットの名前です。最大の特徴は、身体的なサポートをする機能は一切なく、「気持ちのケア」を行うことに特化したロボットだそうです。まるで、ドラえもんやベイマックスが、さらに優しくなったみたいです。

さて、どんなに素晴らしいプロジェクトでも、「現場で実際に使われるようになる」普及フェーズに至るまでには、多くのハードルがあります。
被介護者を目的とした結果、現場にたずさわる他の人間の立場を考慮できていない場合、大きく日の目を見ることはないでしょう。
研究者たちの調査によって明らかになった、ソーシャルロボットMARIOに対する色々な立場の人間からの意見は、どのようなものだったと思いますか?
さまざまな角度から見てみると・・・
107人の利害関係者
アイルランドの研究者Dympna Caseyたちは、107人の利害関係者へのインタビューを綿密に行いました。その利害関係者とは、以下のような立場の方々でした。
- 介護者
- 施設管理者
- 認知症を持つ被介護者
- 被介護者の家族、親戚
そしてインタビュー結果をデータ化し、分析を行いました。
「ともだちみたい」
まず、MARIOを、どう認識しているか。
これに関しては、立場にかかわらず「友達のような存在」だと認識している方がほとんどのようでした。
そして、MARIOの影響はあるのか。
これに関しては、立場によって意見が少し変わりました。認知症を持つ被介護者やその家族、親戚にとっては、MARIOの影響は驚くほどポジティブで、これによって孤独感が軽減されるという意見を持ちました。しかし介護者たちは、「たしかにプラスの影響はあるが、短期的で一時的なものだと思う。長期的な重要性を確信するにはもっと時間が必要だ」という意見をもつようでした。
さらに、認知症ケアにおけるソーシャルロボットの可能性について。
あらゆる立場の人々が概ね前向きな意見を持つ中、一部、「ロボットが人間のかわりにコミュニケーションを行ったり、介護者の代わりになるべきではない」という懸念が出てきました。
さらに、「認知症の段階によるのではないか」という意見には全員が同意しました。「軽度の認知症の人々にとってはロボットは有効なツールだ。しかし、重度の認知症の人々にとっては、タッチスクリーンなど基本的なインタフェースでも難しくなってしまうため、不向きかもしれない」というものでした。
概して、介護現場でのソーシャルロボットのプラスの影響には期待していいと、報告は結ばれています。ただし、明確な結論を出すことはまだ難しいとも。
人間とロボットの関係はどうなるのか
今回参照した論文には、議論のポイントとして、「この先の人間とロボットの関係」があると記されていました。
介護の用途に関わらず、人間とロボットが友人のようにコミュニケーションをとるべきかどうかについては、研究者の中で大きく意見が割れているのだそうです。
研究者の中で意見が割れているということは、法律にも、教科書にも、その答えが載っていないということです。このようなときは、いろいろな情報を集めた上で、自分の意見を持つことが必要ですね。

たとえ答えのない問いだったとしても、なにか感じるものがあれば、ぜひ周囲と意見を交わしてみましょう!


 はてブ
はてブ