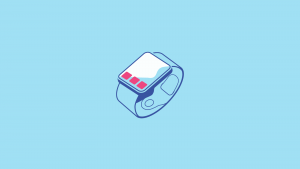この記事の要点
- 科学的介護推進体制加算とは科学的介護を推進するために追加された介護報酬加算
- 科学的介護推進体制加算を受けるにはLIFE利用とPDCAサイクルの取り組みが必要
- 科学的介護推進体制加算では報酬アップだけでなくサービス品質向上も期待できる
2021年4月より介護報酬に「科学的介護推進体制加算」の項目が追加されました。
科学的介護推進体制加算とは一体どのような制度で、介護事業所にはいくら加算されるのでしょうか。また加算を申請するためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
今回は科学的介護推進体制加算についてわかりやすく解説します。
目次
科学的介護推進体制加算(LIFE加算)とは

科学的介護推進体制加算とは、令和3年度介護報酬改定の際に新たに追加された介護報酬の加算制度です。科学的介護情報システム「LIFE」の運用開始に伴い新設した制度であるため、別名「LIFE加算」とも呼ばれています。
政府は科学的介護推進体制加算の支給を行うことにより、現在推し進めている科学的介護情報システム「LIFE」の利用率を増加させ、ひいては科学的介護を介護業界に広めて介護サービスの質を向上させたいという狙いがあります。
対象サービスと加算単位
科学的介護推進体制加算の対象となる介護事業所は、施設系サービス・通所系サービス・居住系サービス・多機能系サービスを提供する介護事業所です。
ほぼすべての介護事業所が加算対象となりますが、加算単位は介護サービスの種類や提供データの内容により異なります。
次に科学的介護推進体制加算の対象となるサービスを種類ごとにご紹介します。

加算単位40の介護サービス
以下の介護サービスは科学的介護推進体制加算がすべて40単位/月になります。
なお加算対象となるサービスには、介護だけでなく介護予防も含まれます。
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
加算単位40・50の介護サービス
以下の介護サービスはLIFEへの提供データの内容により、加算単位がⅠ(40単位/月)とⅡ(50単位/月)に分かれます。
科学的介護推進体制加算Ⅱを申請する場合は、Ⅰで提出が必要なデータに加え要介護者の疾病の状況や服薬情報等の情報も提出する必要があります。
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
加算単位40・60の介護サービス
以下の介護サービスもLIFEへの提供データの内容によりⅠとⅡに分かれますが、Ⅱの加算単位は60単位/月となる点が異なります。
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
科学的介護とは
科学的介護とは、内閣に設置された日本経済再生本部「第7回未来投資会議」(2017年4月)で登場した「科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護」を意味する言葉です。
介護サービスを行うことによってどのような効果が見られたのかを科学的に分析して、効果的だと考えられる方法を知ることができれば、そのサービスを次の要介護者に提供できるようになります。
科学的介護については以下の記事でも詳しく解説しています。
▶「科学的介護」とは何か。LIFEにどう対応するか(解説動画もあり)
科学的介護情報システム(LIFE)とは
科学的介護推進体制加算の制定とともに運用が開始されたLIFEは、上記で説明した科学的介護の分析に必要なデータを収集するためのシステムです。
厚生労働省では2018年より運用が開始された通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム「VISIT」と、2020年より運用が開始された高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム「CHASE」により、以前から科学的介護の準備を行っていました。
2021年4月からは「VISIT」と「CHASE」を一本化した「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence」によって総合的な介護データ収集を推進しようとしています。
科学的介護推進体制加算の算定要件
科学的介護推進体制加算の算定要件は以下の6点です。
- 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の算定要件
- 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の算定要件
- LIFEへのデータ提出
- 介護報酬改定に関するよくあるご質問
- LIFEフィードバック機能の活用
- PDCA サイクルの取り組み
次に6つの算定要件について詳しく説明します。
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の算定要件
利用者ごとの基本情報を「LIFE(科学的介護情報システム)」を通して、厚生労働省に提出する必要があります。
提出しなければならない基本情報とは何なのでしょうか?
以下の4つを参考にしてください。
- 利用者ごとのADL値
- 口腔機能
- 栄養状態
- 認知症の状態その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の算定要件には、以下の2つがあります。
1.各入所者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること
2.必要に応じ、計画を見直すなどサービス提供に当たって、上記1に規定されている情報やその他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること
介護老人福祉施設で算定要件を行うには上記2つを算定する必要があります。
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の算定要件
科学的介護推進体制加算(II)の算定要件は、科学的介護推進体制加算(I)に規定されている算定要件に加え、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出している必要があります。
LIFEへのデータ提出
科学的介護推進体制加算を申請する介護事業所は、介護サービスを利用した要介護者に関するデータを、サービス提供月の翌10日までにLIFEへデータ提出する必要があります。
提出するデータは以下のとおりです。
- 利用者の保険番号、生年月日、性別
- 日常生活自立度(障害高齢者または認知症高齢者の場合)
- ADL(日常生活動作)の状況
- 口腔状態
- 栄養状態
- 認知症の症状または兆候
- Vitality Index(意欲の指標)の段階
また、科学的介護推進体制加算(Ⅱ)の算定要件が適用される事業所は、上記に加えて既往症や服薬情報のデータも提出が必要です。
必須項目・任意項目
科学的介護推進体制加算の評価・提出項目は、必須項目と任意項目の2種類があります。
以下に必須項目と任意項目に分けてご紹介します。
必須項目
| 項目/種別 | 通所・居住サービス | 施設サービス |
| 基本情報 | ・保険者番号 ・被保険者番号 ・事業者番号 ・生年月日 ・性別 | ・保険者番号 ・被保険者番号 ・事業所番号 ・生年月日 ・性別 |
| 総論 | ・食事 ・椅子とベッド間の移乗 ・整容 ・トイレ介助 ・入浴 ・平地歩行 ・階段昇降 ・更衣 ・排便コントロール ・排尿コントロール | ・既往歴 ・服薬情報 ・同居家族等 ・家族等が介護できる時間 ・食事 ・椅子とベッド間の移乗 ・整容 ・トイレ介助 ・入浴 ・平地歩行 ・階段昇降 ・更衣 ・排便コントロール ・排尿コントロール |
| 口腔・栄養 | ・身長 ・体重 ・口腔の健康状態 ・誤嚥性肺炎の発症 ・既往 | ・身長 ・体重 ・低栄養状態のリスクレベル ・栄養補給法 ・経口摂取 ・嚥下調整食の必要性 ・食事形態 ・とろみ ・食事摂取量 ・必要栄養量 ・提供栄養量 ・血清アルブミン値 ・口腔の健康状態 ・誤嚥性肺炎の発症 ・既往 |
| 認知症 | ・認知症の診断 ・日常的な物事に関心を示さない ・特別な事情がないのに夜中起き出す ・特別な根拠もないのに人に言いがかりをつける ・やたらに歩き回る ・同じ動作をいつまでも繰り返す ・意思疎通 | ・認知症の診断 ・日常的な物事に関心を示さない ・特別な事情がないのに夜中起き出す ・特別な根拠もないのに人に言いがかりをつける ・やたらに歩きまわる ・同じ動作をいつまでも繰り返す ・意思疎通 |
任意項目
| 項目/種別 | 通所・居住サービス | 施設サービス |
| 総論 | ・既往歴・服薬情報・同居家族等・家族等が介護できる時間・在宅復帰の有無等 | ・在宅復帰の有無 |
| 口腔・栄養 | ・褥瘡の有無 | ・褥瘡の有無 |
| 認知症 | ・同じことを何度も何度も聞く ・よく物を無くしたり、置き場所を間違えたり、隠したりする ・昼間、寝てばかりいる ・口汚く罵る・場違いあるいは季節に合わない不適切な服装をする ・世話をされるのを拒否する ・物を貯め込む・引き出しや箪笥の中身を全部だしてしまう ・起床・食事・排せつ・リハビリ・活動 | ・同じ事を何度も何度も聞く ・よく物をなくしたり、置き場所を間違えたり、隠したりする ・昼間、寝てばかりいる・口悪く罵る ・場違いあるいは季節に合わない不適切な服装をする ・世話をされるのを拒否する ・物を溜め込む・引き出しや箪笥の中身を全部出してしまう・起床・食事・排せつ ・リハビリ・活動 |
提出期限や提出頻度
LIFEへの提出頻度は、利用者ごとに定められた月の翌月10日までに提出する必要があります。
また、少なくとも6か月に1回以上「科学的介護推進に関する評価」を実施しなければなりません。
利用者ごとの詳細は下記の内容です。
(1)算定を開始しようとする月において、サービスを利用している方(既存)は算定を開始しようとする月の翌日10日までに提出
(2)算定を開始しようとする月の翌日以降にサービスの利用を開始した方(新規)は、サービスの利用を開始した月の翌日10日までに提出
(3)2回目以降の情報提供者は、最低6ヶ月ごとに提出
(4)サービスの利用を終了する利用者は、サービス利用終了月の翌月10日までに提出
LIFEへのデータ提出を要件とする各加算は、すべて翌月10日までにデータLIFEへ提出する必要があります。
やむを得ない場合を除き、翌日10日までにデータ提出ができない場合は利用者全員について算定ができなくなり、事業者にとっても大きなマイナスになってしまうので「翌月10日」までの提出を忘れないようにしましょう。
例)4月の情報を5月10日までに提出が行えない場合、直ちに届出が必要です。また、4月サービス提供分から算定ができません。
もし、情報を提出すべき月に提出が行えない場合には、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出をする必要があります。
また、データ提出の期限(猶予期間)は、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情がある事業所・施設については、猶予期間が下記のように設けられています。
- 令和3年4月〜9月末までに算定開始する場合は令和3年10月10日まで
- 令和3年10月〜令和4年2月末日までに算定開始する場合は令和4年4月10日まで
科学的介護推進体制加算(LIFE)で必要なデータ提出頻度と毎月の作業を効率化するポイント
介護報酬改定に関するよくあるご質問
介護報酬改定によって様々な疑問が生まれます。よくある質問について回答とともにご紹介していきます。
Q1.要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、全て提出すること」とされていますが、この「やむを得ない場合」とはどのような場合なのでしょうか?
A1.「やむを得ない場合」とは情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定が当該利用者について情報の提出ができなかった場合、システムトラブル等により提出ができなかった場合、利用者単位で情報の提出ができなかった場合です。
Q2.LIFEに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれますが、情報の提出の際、利用者の同意は必要ですか?
A2.情報の提出には利用者の同意は必要ありません。LIFEの利用者登録の際に、個人情報を入力しますが、LIFEのシステムには、その一部を匿名化した情報が送られるので、個人情報を収集するものではありません。
Q3.加算を算定しようと考えていますが、入所者のうち1人だけでも加算の算定に係る同意が取れない場合には算定はできないのですか?
A3.加算の算定にかかわる同意が得られない利用者・入居者がいる場合でも、当事者を含む原則全ての利用者か入所者にかかわる情報を提出すると、加算の算定にかかわる同意が得られた利用者か入所者について算定が可能です。
LIFEフィードバック機能の活用
LIFEは各介護事業所から集めたデータを解析し、解析結果をLIFEのウェブサイトを通じて介護事業所にフィードバックします。
これまでに公開されたフィードバックは2021年5月および8月の2回です。LIFEは今後、フィードバック結果を毎月公開する予定としています。
介護事業所はLIFEにデータ提供をするだけでなく、フィードバック機能も活用することが求められています。
PDCAサイクルの取り組み
LIFEへの提出データおよびLIFEからのフィードバックを元にして、今度は利用者に対して行っていた介護サービスが本当に効果的だったかを検証します。
この一連の流れをPDCAサイクルと呼びます。PDCAとは「PLAN(計画)」「DO(実行)」「CHECK(評価)」「ACTION(改善)」の頭文字をとった略称です。
PDCAサイクルは以下のような流れで行います。
- PLAN(計画):ケアプランの作成
- DO(実行):ケアプランに基づいた介護サービスの実践
- CHECK(評価):フィードバックを元としたサービスの検証
- ACTION(改善):検証結果を踏まえたケアプランの改善
介護報酬加算だけではないLIFEのメリット

上記で説明した3点を行うことにより科学的介護推進体制加算の算定要件は満たされますが、LIFEを活用することで発生するメリットは金銭的なものばかりではありません。
データ提出のために自所の介護サービスを確認し、それをフィードバック結果と照らし合わせ、PDCAサイクルで改善策を実行することで、サービスの向上が期待できます。
利用者は質の良いサービスを受けられることとなり、介護事業所はトラブルの防止・業務の効率化・利用者の増加による経営の安定性が期待できます。
つまりLIFEの活用によって、利用者にも介護事業所にもメリットが生じるのです。
まとめ
今回は科学的介護推進体制加算について解説しました。
LIFEはまだ始まったばかりのシステムであり、このシステムを充実させていくためには各介護事業所の協力が不可欠です。
科学的介護推進体制加算を利用しながらLIFEの拡充に協力し、すべての介護事業所が一丸となって日本の介護を向上させていきましょう。




 はてブ
はてブ